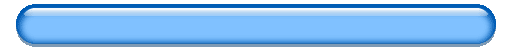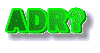ADRと専門的知見を要する審理について
追加
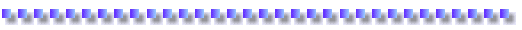
弁護士永島賢也 2001年3月27日

ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの頭文字で、裁判所外紛争処理制度と訳されております。
例えば、
米国yahoo!のGovernment > Law > とたどってくると、CategoriesにAlternative Dispute Resolution という項目があります(dir.yahoo.com/Government/Law/)。
カナダyahoo!にも
英国yahoo!にもあります。
しかし、日本版yahoo!にはそのカテゴリーはないようです。もしかすると、米国・英国等海外では、ADRはよくある当たり前のサービスとして認知されているのに、我が国ではそこまで浸透していないということなのかもしれません。

我が国においてADRといえば、
・建築紛争に関する建設工事紛争審査会、
・住宅の品質確保促進に関する住宅紛争審査会、
・公害に関する公害等調整委員会、
・海上運送船舶に関する日本海運集会、
・工業所有権に関する工業所有権仲裁センター(最近はドメイン名紛争も取り扱っています)
などがあります。

このように、ADRは、紛争解決に関する裁判所以外の他の選択肢という意味がありますが、必ずしも、裁判所以外のものに限るものではないといわれています(古閑裕二・法曹界編「アメリカにおける民事訴訟の実状」)。
つまり、裁判所設営型のADRもあるとのことです(
Court Sponsored ADR)。
例えば、東京地方裁判所民事第22部(調停部)は、「専門家の助言を活用した紛争解決の勧め」と題するパンフレットを配布しています。
これによると、「建築関係事件、コンピュータ関連事件、不動産関連事件等の専門的知識が不可欠な紛争の調停手続による適正、迅速な解決を推進しています。」とのことです。
当該調停部には、建築士、不動産鑑定士、医師、コンピュータ技師等の専門資格者が多数所属しており、調停主任である裁判官と、これら専門家委員・法律家委員とが協力して事件の解決を行っています。
これは、裁判所設営型のADRともいえます。
 専門的な知見
専門的な知見を簡易に利用する方法としてはかような調停制度を利用するのが有効です。(「専門的な知見を必要とする民事訴訟の運営」・司法研修所編)。
争点整理の早期の段階で事件を調停に付し、専門家調停員の協力を得て争点整理を行うことができるからです。 通常、訴訟運営は、おおまかな審理計画策定→争点整理→証拠調べというサイクルで行われるといわれています。
ここでポイントとなるのは、証拠調べという段階ではなく、その前の争点整理という段階で専門家の知見を利用することができる点です。

専門家の知見を訴訟に生かす方法としては、鑑定という手続があります。
鑑定とは、裁判官の判断能力を補充するために特別な学識経験を有する第三者にその専門知識またはこれに基づく事実判断について報告させる証拠調べのことで、この報告を行う者を鑑定人といいます。
つまり、鑑定が証拠調べである限り、その前段階である争点整理段階において専門的知見を利用しづらいことになります(もっとも、「釈明処分としての鑑定」という手段はあります・民訴151条1項5号。)。
それゆえ、鑑定を行う以前に、鑑定の対象となる資料をなるべく多く確保しておこうとして、むしろ争点についてはこれをあえて絞らないまま一応医師などの証人尋問を行ってしまうこともありえます。
他方、争点整理を目的とする証拠調べとしての鑑定を採用することも可能ですが、争点整理を行った鑑定人とその後の証拠調べを行う鑑定人とが同一人物であると、当事者から異論や不満がでやすいというデメリットがあります。争点整理の過程で当該鑑定人による鑑定が当事者のいずれの側に有利か不利かが予め予想がついてしまうからです。
民事訴訟規則133条は、鑑定人が審理に立ち会い、証人に問いを発する権限があることを定めています。
これは、争点整理段階というできるだけ早期に専門的知見を利用することを推進するという価値判断をもって定められたといえます。

それを更に前倒しし、専門的知見を更に早期に利用するため、争点整理の早い段階で専門家の揃った調停部に付するという方法がクローズアップされるものと考えます。
思うに、かようなケースで付調停とされる場合、それが、争点整理を目的としているのか、あるいは、話し合いによる解決を目的としているのか、十分確認しておくことが重要になると考えます。
ほとんどの場合、争点整理も合意形成も両方目的であるということになるとは思うのですが、これをあえて明確に区別させ、合意形成による解決がメインであるのなら、その調停の期間を例えば6ヶ月なら6ヶ月と区切ることも必要かと思います。
そして6ヶ月を経過して調停が成立しないときは本案部に戻して再び訴訟を進行させるべきではないかとも思います。
他方、争点整理がメインの目的の場合は、むしろ、弁論と同様という意識をもって準備書面等を専門家である調停委員とも話し合いながら積極的に提出しなければならないと思います。
そして、調停部の作成した争点整理表を双方当事者に開示してもらうことが重要と考えます。

ところで、前述の東京地裁民事22部は、平成13年4月1日、
建築関係事件の集中部として発足します。
つまり、同日以降に提起された訴訟は、最初から民事22部が担当し、判決まで行うということです。
これは、本案部→付調停→本案部という連携がより緊密のなるということです。
おそらく、民事22部に所属している専門家は建築士が一番多いようですから、建築関連の紛争について最も成果をあげているということなのではないかと思います。

裁判所設営型ADR
・
仲裁(Arbitration)
(Mandatory or Voluntary, Non-binding)
・
簡易トライアル(Summary Trial)
・
ENE(Early Neutral Evaluation)
(訴訟の早期の段階で第三者たる法律家に事件の要旨を報告してその評価を受けることによって事件に対する見通しをつける手続)
・
調停(Mediation)
・
和解(Settlement Conference)
・
ミニトライアル(Mini Trial)
・マジストレイト(Magistrate)
・
スペシャルマスター(Special Master)
前掲書 26ページ以下参照

集中部継続の要件
1 建物に関する請負代金または売買代金の請求事件で、設計・施工・監理の瑕疵、工事の完成、工事の追加変更、設計監理の出来高が争点となるもの
2 建物の設計・施行・監理の瑕疵、または工事の未完成を原因とする損害賠償請求事件
3 工事に伴う振動・地盤沈下に基づく建物に関する損害賠償請求事件