


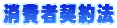
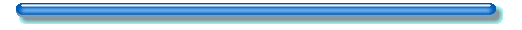 2001年12月21日 弁護士保坂光彦
2001年12月21日 弁護士保坂光彦
 消費者契約法という法律が制定され、平成13年4月1日から施行されました。
消費者契約法という法律が制定され、平成13年4月1日から施行されました。
 この法律は、事業者と消費者との間の情報力や交渉力と言った力の格差を少しでも埋め消費者の利益を養護することを目的としており、事業者と消費者との間の契約(労働契約を除く)全般に適用されるかなり適用範囲の広い法律となりました。
この法律は、事業者と消費者との間の情報力や交渉力と言った力の格差を少しでも埋め消費者の利益を養護することを目的としており、事業者と消費者との間の契約(労働契約を除く)全般に適用されるかなり適用範囲の広い法律となりました。
 この法律によって消費者保護のために新設された制度の目玉は大きく分けて「契約者取消権」と「不当条項の無効化」の二つです。
この法律によって消費者保護のために新設された制度の目玉は大きく分けて「契約者取消権」と「不当条項の無効化」の二つです。
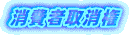
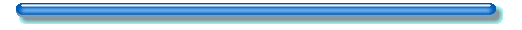
 かつてこの法律が出来るまでの間、不当な勧誘方法などによる消費者被害の救済については民法の「詐欺」や「強迫」、「錯誤」といった規定により対処されてきましたが、もともと民法は対等な当事者同士を念頭に置いている法律であるため取消や無効を認められるための要件が厳しく、「詐欺」や「強迫」とまでは行かなくとも不当だと考えられる勧誘方法による被害者を救済することが困難とされていました。
かつてこの法律が出来るまでの間、不当な勧誘方法などによる消費者被害の救済については民法の「詐欺」や「強迫」、「錯誤」といった規定により対処されてきましたが、もともと民法は対等な当事者同士を念頭に置いている法律であるため取消や無効を認められるための要件が厳しく、「詐欺」や「強迫」とまでは行かなくとも不当だと考えられる勧誘方法による被害者を救済することが困難とされていました。
 そこで、そのような事例においてもより簡単に契約の取消が可能となるように制定されたのが消費者取消権です。
そこで、そのような事例においてもより簡単に契約の取消が可能となるように制定されたのが消費者取消権です。
 もっとも、消費者取消権といっても、クーリングオフのように消費者が取消をすることが出来るわけではなく、法律により定められた「誤認」「不退去」「監禁」といった類型に当てはまる場合にのみ認められることになります。
もっとも、消費者取消権といっても、クーリングオフのように消費者が取消をすることが出来るわけではなく、法律により定められた「誤認」「不退去」「監禁」といった類型に当てはまる場合にのみ認められることになります。
 まず「誤認」とは、「重要な事項」に関し事実に反することを告げたり、もともと不確実であるはずの事項に関して断定的な判断を提供したり、または消費者にとって不利益な事実を敢えて告げないといった不当な勧誘がなされ、それによって消費者が「誤認」して契約してしまった場合を言い、この場合「(民法上の)詐欺・錯誤」とまでは言えない場合でも取り消すことが出来ます(「絶対値上がりします。」などと言って勧誘するのはその典型でしょう。)
まず「誤認」とは、「重要な事項」に関し事実に反することを告げたり、もともと不確実であるはずの事項に関して断定的な判断を提供したり、または消費者にとって不利益な事実を敢えて告げないといった不当な勧誘がなされ、それによって消費者が「誤認」して契約してしまった場合を言い、この場合「(民法上の)詐欺・錯誤」とまでは言えない場合でも取り消すことが出来ます(「絶対値上がりします。」などと言って勧誘するのはその典型でしょう。)
 次に、事業者が消費者の住居や職場から退去せず、消費者が契約するまで居座るような場合を「不退去」と言い、逆に事業者が消費者を自己の事務所などから契約するまで一歩も出させないような場合を「監禁」(もちろん、牢屋のように物理的に監禁されている必要はなく、事実上帰れないような雰囲気が存在している場合でも良いと考えます。)と言い、この場合「不退去」「監禁」の状態を脱するためにやむなく結んだ契約は「(民法上の)強迫」とまでは言えない場合であっても取り消すことが出来ます。
次に、事業者が消費者の住居や職場から退去せず、消費者が契約するまで居座るような場合を「不退去」と言い、逆に事業者が消費者を自己の事務所などから契約するまで一歩も出させないような場合を「監禁」(もちろん、牢屋のように物理的に監禁されている必要はなく、事実上帰れないような雰囲気が存在している場合でも良いと考えます。)と言い、この場合「不退去」「監禁」の状態を脱するためにやむなく結んだ契約は「(民法上の)強迫」とまでは言えない場合であっても取り消すことが出来ます。
 ちなみに、民法の規定よりも取り消せる場合を広くするという観点からすると、上記の類型の他にも「威迫」「困惑」類型といったものも考えられますが、今回の立法では採用されませんでした。
ちなみに、民法の規定よりも取り消せる場合を広くするという観点からすると、上記の類型の他にも「威迫」「困惑」類型といったものも考えられますが、今回の立法では採用されませんでした。
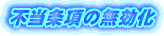
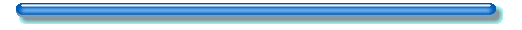
 この法律が成立する前には(場合によっては成立後も)情報力と交渉力を有する事業者によって、消費者にとって一方的不利となる契約条項が不動文字で挿入されており後々トラブルに発展する事が少なくありませんでした。
この法律が成立する前には(場合によっては成立後も)情報力と交渉力を有する事業者によって、消費者にとって一方的不利となる契約条項が不動文字で挿入されており後々トラブルに発展する事が少なくありませんでした。
 そこで、本法により消費者にとって一方的に不利な条項は無効とし、そのような条項から消費者を解放することとされました。
そこで、本法により消費者にとって一方的に不利な条項は無効とし、そのような条項から消費者を解放することとされました。
 まず、該当する規定は全て無効となる絶対的無効条項(いわゆるブラックリスト)が規定されています。(ちなみに、今回の立法においては「事案によっては無効となりうる条項」いわゆるグレイリストは規定されませんでした。)
まず、該当する規定は全て無効となる絶対的無効条項(いわゆるブラックリスト)が規定されています。(ちなみに、今回の立法においては「事案によっては無効となりうる条項」いわゆるグレイリストは規定されませんでした。)
 そこでまず第1に挙げられているのが事業者の損害賠償責任を免除する条項は無効とされています。
そこでまず第1に挙げられているのが事業者の損害賠償責任を免除する条項は無効とされています。
 もっとも、全部免除する条項は全て無効とされていますが、事業者側に軽過失しかない場合において損害賠償義務の「一部」を免除する条項は無効とならないこととされているのでその限度では有効と言うことになります。(但し、例えば損害の90%を免除するというような「全部免除」ではないが実質的には全部免除の近いような不当条項については後に述べる包括的規定により無効とされることになると思われます。)
もっとも、全部免除する条項は全て無効とされていますが、事業者側に軽過失しかない場合において損害賠償義務の「一部」を免除する条項は無効とならないこととされているのでその限度では有効と言うことになります。(但し、例えば損害の90%を免除するというような「全部免除」ではないが実質的には全部免除の近いような不当条項については後に述べる包括的規定により無効とされることになると思われます。)
 逆に、消費者から事業者に支払われるべき損害賠償額を不当に増額させる規定も無効とされます。
逆に、消費者から事業者に支払われるべき損害賠償額を不当に増額させる規定も無効とされます。
 例えば、消費者が契約を解約する際に、同種の事案において現実に生じる損害の平均額が契約金の1割相当に過ぎないにも係わらず、「契約金額の8割を違約金として支払う」というような規定は、平均額(1割)を超える部分すなわち残り7割の部分については無効とされることになります。(なお、消費者からの支払が遅延したことにともなう遅延損害金については年率14.6%を超える部分が無効とされることになっています。)
例えば、消費者が契約を解約する際に、同種の事案において現実に生じる損害の平均額が契約金の1割相当に過ぎないにも係わらず、「契約金額の8割を違約金として支払う」というような規定は、平均額(1割)を超える部分すなわち残り7割の部分については無効とされることになります。(なお、消費者からの支払が遅延したことにともなう遅延損害金については年率14.6%を超える部分が無効とされることになっています。)

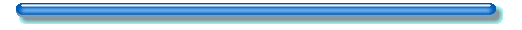
 以上のように、本法の施行によって消費者取消権が認められたり、不当条項を無効とすることが定められ消費者側の力は強化されましたが、実際の裁判などにおいて具体的にどのような場合に取消が認められるのか、またどのような条項が無効とされるのかについてはまだまだ不明確な部分もあり今後の裁判例などの集積を待たねばなりませんし、なによりも本法の第3条2項に「(消費者は)事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について努めるものとする」と書かれているように、消費者自身も裁判その他のトラブルを未然に回避するべく「賢く」なることが求められています。
以上のように、本法の施行によって消費者取消権が認められたり、不当条項を無効とすることが定められ消費者側の力は強化されましたが、実際の裁判などにおいて具体的にどのような場合に取消が認められるのか、またどのような条項が無効とされるのかについてはまだまだ不明確な部分もあり今後の裁判例などの集積を待たねばなりませんし、なによりも本法の第3条2項に「(消費者は)事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について努めるものとする」と書かれているように、消費者自身も裁判その他のトラブルを未然に回避するべく「賢く」なることが求められています。
 何事も「転ばぬ先の杖」が大切ということですね。
何事も「転ばぬ先の杖」が大切ということですね。

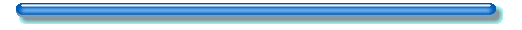
 契約者取消権と同じような効果を上げられる制度としては、みなさんもご存じのクーリングオフがありますが、クーリングオフが可能な期間は契約類型によって異なります。
契約者取消権と同じような効果を上げられる制度としては、みなさんもご存じのクーリングオフがありますが、クーリングオフが可能な期間は契約類型によって異なります。
 以下に参考までに契約類型とクーリングオフの期間を挙げておきます。(なお、起算点は各契約類型によって微妙に異なりますので実際にクーリングオフを為されるときには必ずご確認下さい。)
以下に参考までに契約類型とクーリングオフの期間を挙げておきます。(なお、起算点は各契約類型によって微妙に異なりますので実際にクーリングオフを為されるときには必ずご確認下さい。)
8日
訪問販売・電話勧誘販売・継続的役務提供契約・クレジット契約・宅地建物取引
ゴルフ会員権契約・生保損保契約・小口債券販売契約
10日
投資顧問契約・商品ファンド契約
14日
海外商品先物取引契約・商品預託取引
20日
連鎖販売取引・業務提供誘因販売取引
(次)
 Copyright © 2001 mitsuhiko hosaka, all rights reserved.
Copyright © 2001 mitsuhiko hosaka, all rights reserved.




