


 NEW!
NEW!
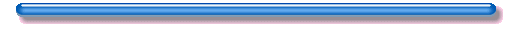 2002年2月6日 弁護士保坂光彦
2002年2月6日 弁護士保坂光彦

 1 会社分割とは文字通りある会社を2つ以上に分割し「営業の全部又は一部を他社ないし新設会社に承継させる」ことを言います。
1 会社分割とは文字通りある会社を2つ以上に分割し「営業の全部又は一部を他社ないし新設会社に承継させる」ことを言います。
改正前は、ストレートに会社を分割するための法制度がなく、現物出資や営業譲渡といった制度を利用して同じような結果を作り出していましたが、法律解釈上の問題のほか、手続や権利関係の調整の面でさまざまな問題点が指摘されていました。
そこで、そのような状況を変えて会社の組織再編がスムースに行われるようにする目的で、平成13年4月1日から「会社分割」が認められるようになりました(会社分割法制事自体の内容や手続などは本稿のテーマではないのでここでは割愛します。)。
なお、ここで言われている「営業」とは「一定の目的の為に組織化され有機的一体として機能する財産」と定義され、物としての営業用財産だけではなく、営業上のノウハウや得意先関係といった無形の財産も含むとされています。
話をわかりやすくするために、例えば大きな総合商社の中にある、食料品事業部、家電製品事業部、金属事業部・・・etcといった複数の事業部門をそれぞれ分割可能な「営業」と考えればイメージが沸きやすいのではないでしょうか。
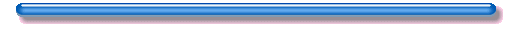
 2 さて、「営業」ごとに会社が切り分けられるとすると、物やノウハウと言ったものだけでなく、そこで事業に従事している「人」(労働者)も一緒に移転すると考えるのが自然ではないかと考えられますが、労働者の立場から見ると「組織再編」「事業再編」などと言われてもそう簡単には割り切れない部分があります。
2 さて、「営業」ごとに会社が切り分けられるとすると、物やノウハウと言ったものだけでなく、そこで事業に従事している「人」(労働者)も一緒に移転すると考えるのが自然ではないかと考えられますが、労働者の立場から見ると「組織再編」「事業再編」などと言われてもそう簡単には割り切れない部分があります。
たとえば、分割により新設される会社(事業部門)が不採算部門としてリストラ対象のいわゆる泥船ではないか(逆に、元の会社に残るとしても分割により元の会社が事実上抜け殻になってしまうのではないか)という不安が予想されます。
また、より直接的な問題としていままでの給与や待遇などがどのようになってしまうのかと言う不安に直面するのではないかと思います。
そこで、会社分割法制及びこれとセットで成立・施行された労働契約承継法において労働者の地位や権利についてどのように定められているかを見ていきたいと思います。
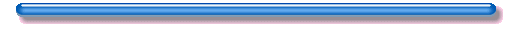
 3 労働者の側からみた会社分割までの流れ
3 労働者の側からみた会社分割までの流れ
(1)労働者(代表)との事前協議
労働者の理解と協力を得られるように、分割計画書等の作成に入る前に労働者達と事前協議をしなければならないことが定められています(労働契約承継法7条)。
ここで言う「労働者」には後に出てくるような区別はなく、全ての労働者に対し、会社分割の理由や分割後の双方の会社の債務履行見込み、そして労働契約の承継に関する事項などの説明・協議を行う必要があります。
具体的には全労働者の過半数を代表する者(要するに労働組合。
一つの組合で過半数に達しない場合は複数の組合の合計が過半数に達すればよい)と協議することと厚生労働省令に定められています。
(2)労働者との個別協議(商法等改正附則5条)
会社は上記の事前協議とは別に、会社分割によって承継される営業に従事している者(ここでは「主として」という限定はない。)との間で、労働契約を承継させるか否かについて協議する必要があります。
後にも述べるように、労働契約承継法により労働者の個別の承諾が無くとも別会社に労働契約を移すことが出来ることになり、民法625条に定められた「使用者は労務者の承諾あるに非ざればその権利を第三者に譲渡することを得ず」という大原則が修正されています。その不都合を少しでも軽減するようにと言う趣旨で設けられた規定です。
この事前協議により労使双方が納得の上で円満に解決されるとすれば真に理想的であり、実務上もそのように運営されることが期待されます。
(3)上記協議が終了した後、労働者への会社分割に関する正式な通知が為されることになります(労働契約承継法2条)。
ここには分割の内容(どの営業が承継されるのか)や時期、そして通知を受ける労働者の地位(承継されるのか否か等)が記載され、労働者に後述の異議権を行使するために必要な情報を与えるという意味を有します。
(4)では、通知を受けた労働者は結局どちらの会社に行くことになるのでしょうか?
これは、2段階に分けて考える必要があります。
まず、第1に会社が作成する分割計画書において承継する労働者として記載されているか否か。この段階では(事前協議の結果はさておくとして)労働者側の意思を働かせる余地はありません。
そして、基本的にはこの分割計画書に記載された通りと言うことになります。
 では、労働者の意向はどうなるのでしょうか?
では、労働者の意向はどうなるのでしょうか?
ポイントは会社分割においてその労働者が承継される営業に「主として」従事しているか否かです。
以下簡単にまとめますと、
①「主として従事」している。分割計画書に承継させる旨の記載あり。
労働者の承諾の有無に係わらず承継される。
②「主として従事」している。分割計画書には承継させる旨の記載なし。
原則として承継されません(元の会社に残留)但し異議権あり。
③「従として従事」している。分割計画書に承継させる旨の記載あり。
原則として承継されます。但し異議権があり。
④「従として従事」している。分割計画書に承継させる旨の記載無し。
承継されず、異議権もありません。(そもそも通知不要とされています)
⑤「営業」にまったく従事せず
記載の有無に係わらず承継無し(仮に記載しても会社分割の効果としては承継されません。)そもそも会社分割制度の対象外だからです。
どうしても承継させたい場合には個別の同意を得た上で転籍の手続きをとる必要があります。
①④⑤の場合には労働者の意向を反映させる余地は結局の所ありません。
(そもそも①が今回の最大の改正点です。)
逆に、労働者側にイニシアティブがあるのは②③の場合です。
ここでは労働者の意向を反映させることが出来ます。
すなわち、労働者が分割企画書に「異議」を述べることにより、今後所属する会社を分割計画書とは逆にすることが出来るのです。
もちろん、異議権を行使しないままにすることも出来ますので、結果として労働者の側で好きな方を選ぶことが出来ることになります。
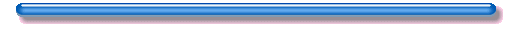
 4 では、上記のように非常に重要な要素である「主として従事」はどのように判断されるのでしょうか?
4 では、上記のように非常に重要な要素である「主として従事」はどのように判断されるのでしょうか?

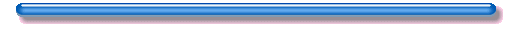 Copyright © 2001 mitsuhiko hosaka, all rights reserved.
Copyright © 2001 mitsuhiko hosaka, all rights reserved.




