



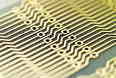

この判決は、交通事故被害者の逸失利益を算定する際の中間利息の控除の割合について、低金利の状況下にあっても、民事法定利率の年5%を採用するのが相当であると判示しました。 現行法は、破産法46条5号、会社更生法114条、民事再生法87条1項1号などをみても、将来の請求権の原価評価に当たっては、法的安定および統一的処理の見地から、一律に法定利率による中間利息の控除をすることが相当であると考えているものということができ、その合理性は首肯できないものではないとしています。 また、交通事故訴訟の統一的処理という観点も含めて判断しています。 |